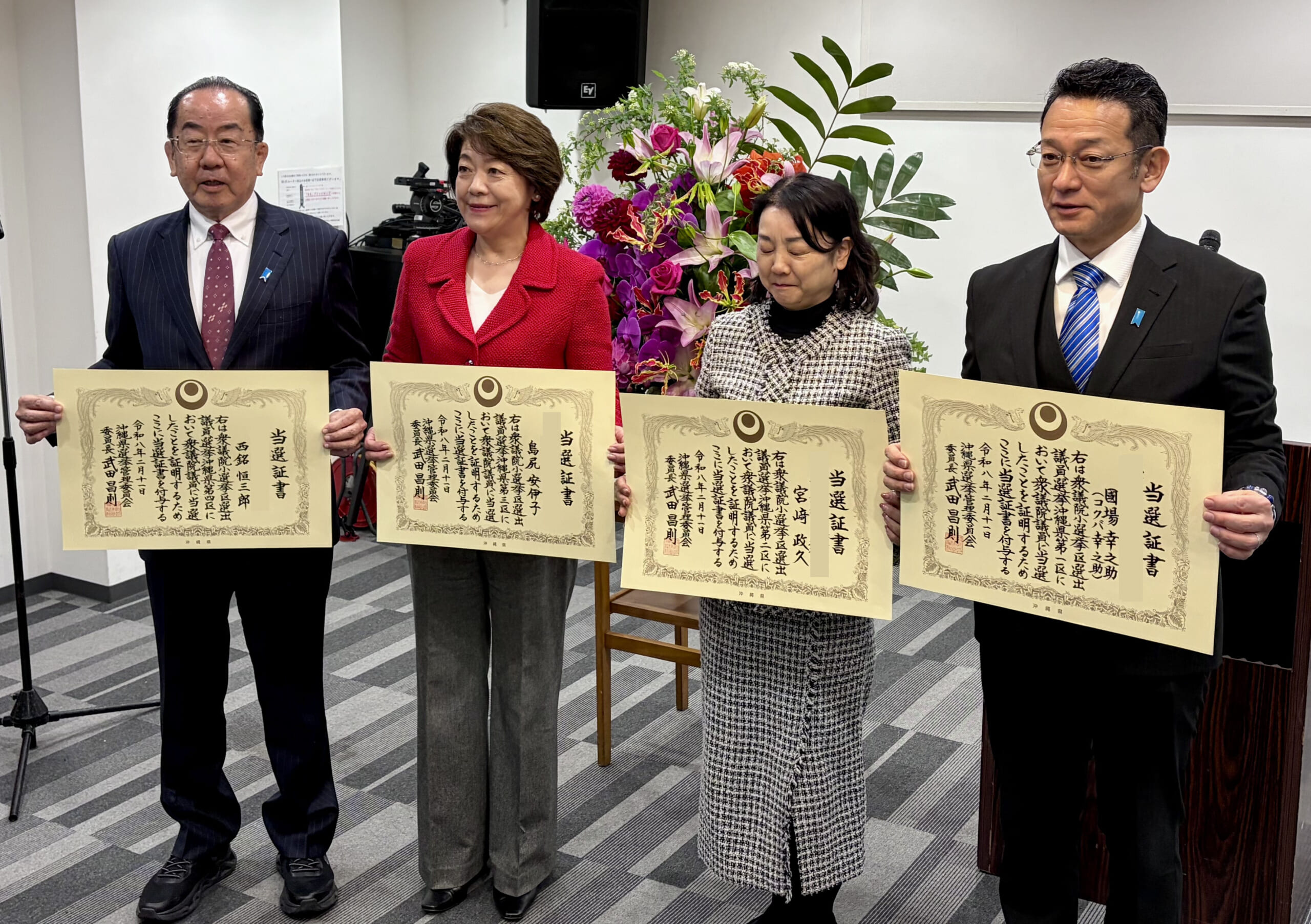【視点】「反省」復活 率直に疑問だ

戦後80年の15日、石破茂首相は政府主催の全国戦没者追悼式で「戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」と述べた。
首相の式辞に「反省」が入るのは民主党政権の野田佳彦首相以来、13年ぶりだ。自民党の政権復帰後、安倍晋三首相以降は一度も使われていない。なぜ今、あえて「反省」の2文字を復活させる必要があるのか、率直に疑問だ。
反省の意を表する前に、日本を取り巻く国際情勢を改めて直視すべきではないか。戦後80年の節目に合わせ、特に中国が歴史認識問題で対日攻勢を強めている。
中国国内では南京事件をテーマにした映画が上映され、国民に旧日本軍の残虐性を印象付ける宣伝が展開されている。中国政府は遼寧省瀋陽にあった旧日本軍の捕虜収容施設に国内外のメディアを招き、日本による捕虜虐待があったと訴えるキャンペーンにも力を入れる。
中国が戦後80年の節目を利用し、第二次大戦における日本の戦争責任をクローズアップしようとする意図は何か。
推測されるのは、まず対日戦勝国として中国共産党の統治を正当化したいという思惑だ。さらには歴史認識問題を外交カードに、国際社会で日本の「封じ込め」を図る狙いが透けて見える。
中国の覇権的な行動で最も影響を受ける沖縄県民からすると、これは極めて深刻な問題である。
台湾有事への懸念にせよ、尖閣諸島周辺での侵略的な行動にせよ、日本が中国に苦言を呈しようとすると、中国政府は、台湾も尖閣諸島も、もともと日本が中国を侵略して「奪ったものだ」と臆面もなく正当化する。侵略国である日本に、口出しする資格はないというのが中国政府のスタンスだ。
中国政府にとって歴史認識とは、国際的な平和構築という未来志向のためにあるのではない。現在進行している中国の侵略的行動に対し、日本を一喝して黙らせるための武器でしかない。
尖閣や台湾に関する中国の長年の振る舞いを見ていると、結局はそういう感想を抱かざるを得ないのである。
日本政府が、中国のこうした底意ある歴史認識に迎合することは断じてあってはならない。
戦後70年に当時の安倍首相は「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」という談話を出した。
それは今なお歴史認識を外交カードに使おうとする他国に対し、安易に同じ土俵には乗らないという決意表明だったと受け取れる。
石破首相が「戦後80年談話」を出すことには自民党内でも反対の声が上がった。首相は談話の見送りを決めたとされる。
だが追悼式の式辞で首相が再び「反省」を持ち出すことは、安倍氏の戦後70年談話と齟齬(そご)をきたさないのか。尖閣や台湾問題への影響も含めて、注視していく必要がある。