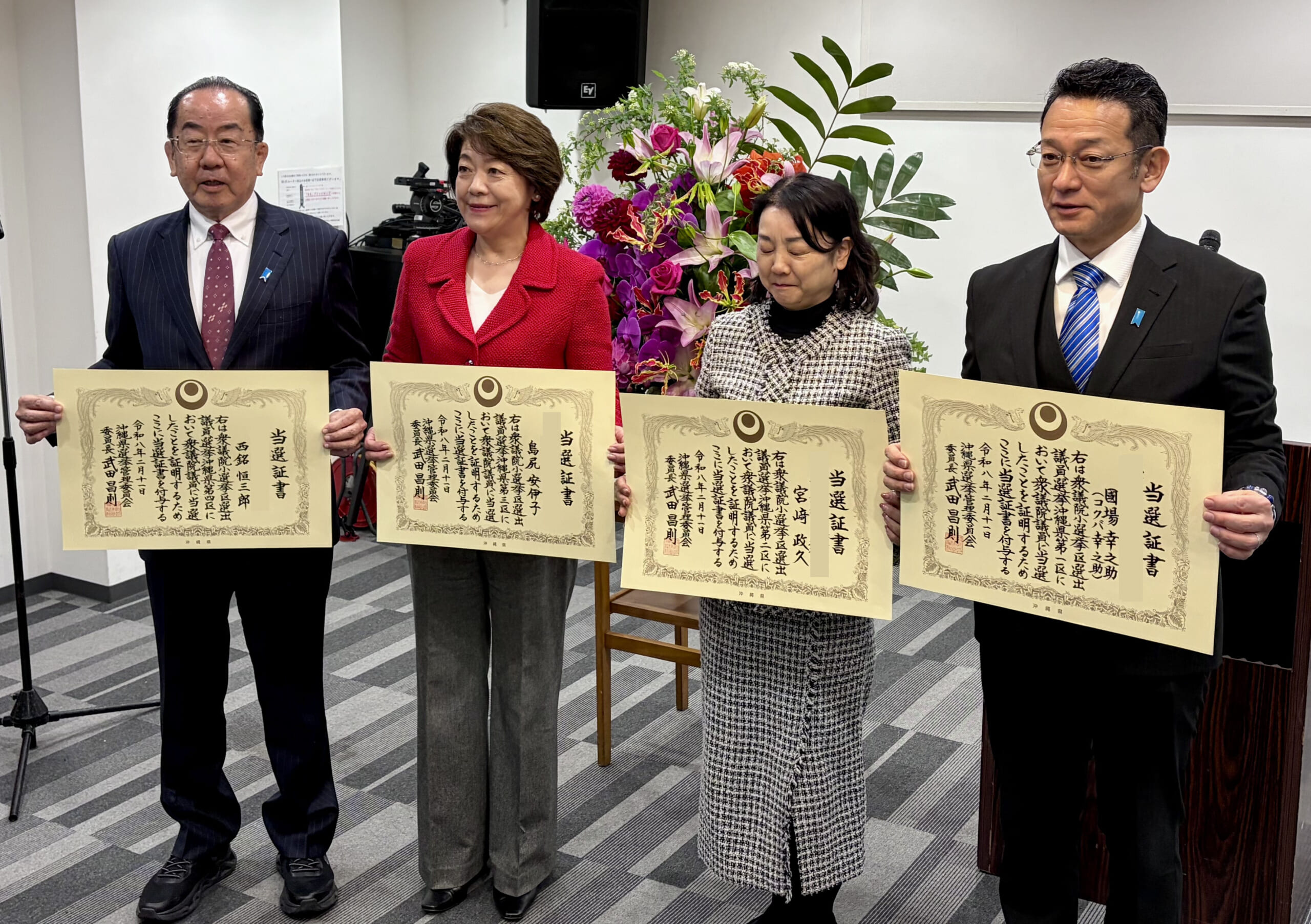【視点】沖縄と本土 分断ではなく協調を

「復帰っ子」は1972年、沖縄が日本に復帰した年に生まれた人たちで、沖縄では今でも、一種の特別な存在として扱われている。沖縄県民にとって復帰とは、長い沖縄の歴史の中でも、また一人ひとりの個人としても、それほどに強烈なインパクトを持つ出来事だった。
県民の本土に向ける眼差しはちょうど、復帰っ子の世代を境目に、大きく性質が変化したような気がする。
復帰っ子以前の世代は、本土と沖縄が分断された時代に育った。互いの無理解もあり、本土に渡った沖縄出身者が露骨に差別されたこともあった。文字通りの「沖縄ヘイト」が横行していた時代である。
当時は本土の人たちに追いつき、追い越したいという意地が、沖縄県民の大きなモチベーションになっていた。米国統治下という逆境の時代にあって、沖縄の地位向上のために努力した先人たちの世代である。本土への感情は愛憎こもごもといったところがある。
復帰っ子以後の世代は、政府の振興予算投入もあって、沖縄が大きく発展した時代に幼少期を過ごした。
沖縄は、自然や文化の薫り高い南国の観光リゾート地として、本土から憧れの対象とみなされるようになった。沖縄出身であることが、むしろ一種のステータスであるかのように見られることも増えた。
インターネットの普及で情報格差も解消され、本土と沖縄の精神的な距離感も縮小した。復帰っ子以後の世代は、ことさら本土と沖縄の関係を特別視する傾向が少ない。若ければ若いほど、ごく自然に本土との一体感が醸成されているように感じる。
しかし現在でも、基地問題や歴史認識を巡り、絶えず本土と沖縄を分断するような出来事が続いている。
米軍普天間飛行場の辺野古移設は、10年前のように沖縄の最重要問題という扱いではもうないが、県と国が対立する構図は、いまだに解消されていない。国土面積約0・6%の沖縄に在日米軍専用施設の7割が集中する重い負担も続く。
歴史認識問題は、西田昌司参院議員の「ひめゆりの塔」発言で再燃した。これに沖縄は抗議一色となった。西田氏は謝罪しながらも自らの歴史観は変えていない。参政党の神谷宗幣代表が西田氏の発言に一定の理解を示し、さらなる波紋を呼んでいる。
基地問題にせよ歴史認識問題にせよ、意見の相違が不毛な対立を生むようなことがあってはならない。今は危うい時期ではないか。
本土の人たちには、苦難を強いられてきた県民の微妙な心情を思いやるデリカシーを持ってほしい。県民も独善的になることなく、対話には常にオープンであるべきだ。
復帰後53年を経て、沖縄は目覚ましい経済的発展を遂げた。復帰の意義を否定する県民はほぼ皆無だろう。米軍基地負担は、どんなに道が遠くても一歩一歩先へ進まなくてはなない課題だ。本土と沖縄がさまざまな違いを乗り越えて協調する姿勢を示してこそ、未来は見てくる。