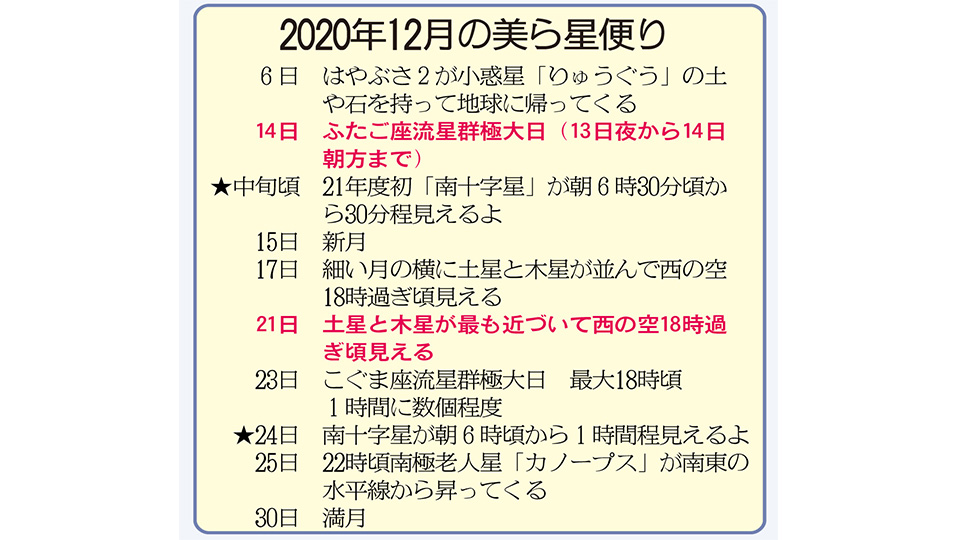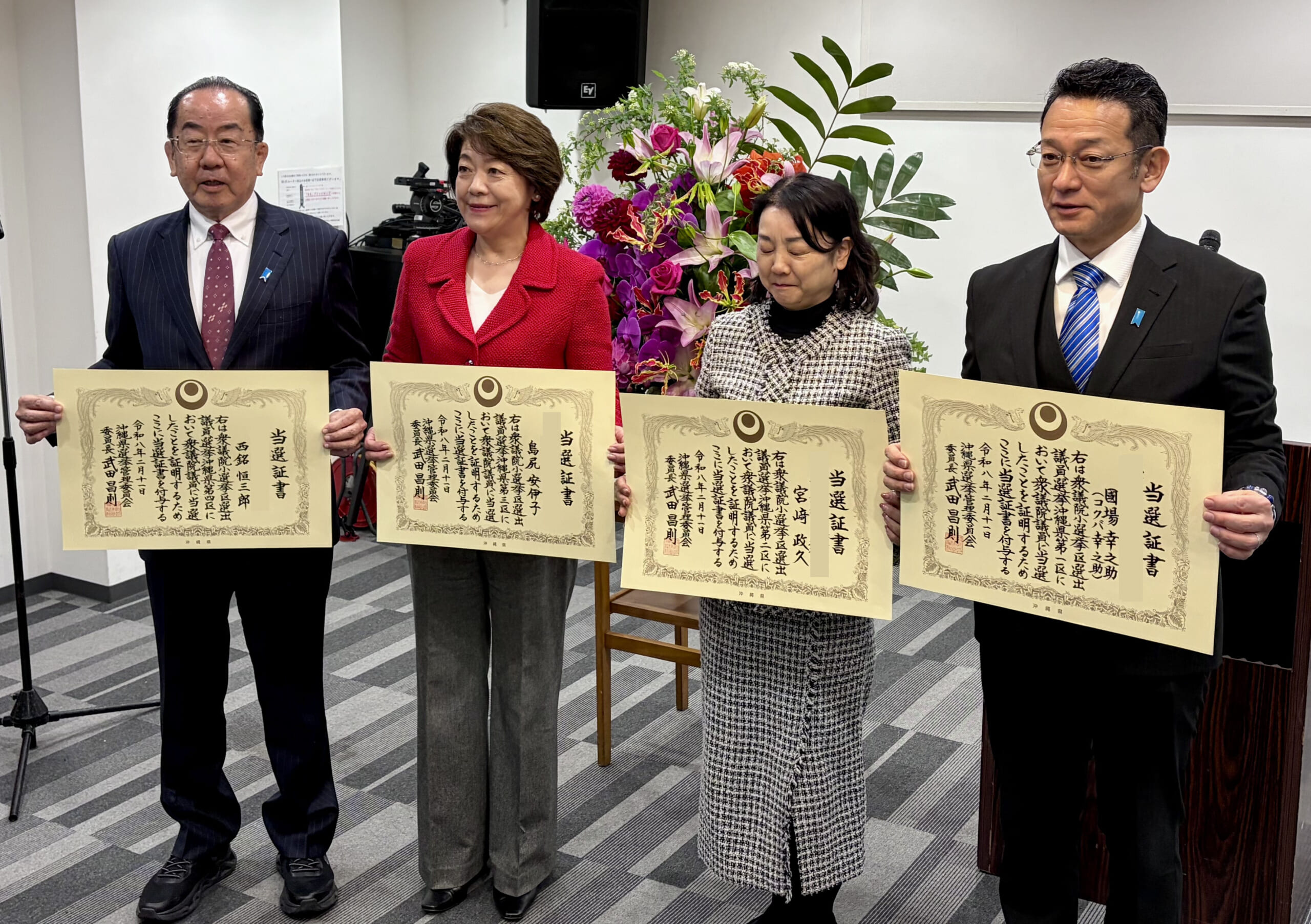【視点】独立論 一足飛びの理想郷はない

沖縄開発庁長官を務めた県出身の政治家、上原康助氏(1932~2017)が沖縄独立をテーマにした草稿を書き残していたことが話題になっている。多くの県民にとって沖縄独立論は机上の空論に過ぎないが、沖縄の日本復帰50年の節目に、沖縄独立論を改めて考え直す必要があるかも知れない。
上原氏の草稿が執筆されたのは95年の米兵による少女暴行事件が起きたころだという。
反基地ムードの高まりを背景に、独立を宣言することで米軍基地の撤去や縮小を実現できるという考えが根底にあったと思われる。
草稿では自身が考える独立について「あくまで日本国民の同意を得た上で、長く連れ添った夫婦がそれぞれの新たな人生のために協議離婚するようなもの」「日本に復帰を果たす中で得られるはずだった繁栄や平和への期待が、実は幻想だと気付いたことに対する当然の帰結だ」と記している。
このような独立論は現在でも沖縄の一部で根強く主張されているが、世論に影響を与えるレベルまで達したことはない。
最大の理由は、基地撤去の「手段」としての独立論のみが先行し、独立後の沖縄が実際にはどのような国家になるのか、曖昧模糊(あいまいもこ)としているからだ。
独立国家としての沖縄を想像したとき、参考になるのは琉球王国時代の姿だろう。アジアで交易の中心地として繁栄した時代は、沖縄の黄金時代としてノスタルジックに語られることも多い。首里城焼失の際に多くの県民が味わった「喪失感」もそうした歴史への憧憬に由来するはずだ。
だが一方で、離島の宮古、八重山では、琉球王国時代の沖縄をポジティブに評価する声は少ない。
首里王府は宮古、八重山のみに人頭税という過酷な税を課し、離島住民には収奪者として臨んだ。当時の離島住民にとって、首里城は圧政の象徴にほかならない。
琉球王国時代の八重山をうかがわせる伝承は悲惨なものばかりだ。民衆を圧迫した首里王府に反抗し、成敗された英雄オヤケアカハチ、王府の命令で他の島に強制移住させられ、恋人同士が引き裂かれたという野底マーペー、与那国島で人減らしの場所だったとされるクブラバリなどが代表例だ。
仮に「琉球共和国」のようなものが誕生したとしても、それが県民、特に離島住民にとって幸せな政治体制になり得るのか。歴史を見る限り大いに疑問である。たとえば基地反対を最優先の国策とし、離島の住民生活を二の次、三の次にする構造的差別の国になりかねないという危惧すら抱く。
振り返れば、沖縄の民主主義や経済的繁栄は、日本という国家と一体不二のものとして構築されてきた。
ロシアのウクライナ侵攻や香港の強権体制成立などを見ると、一つの国に自由主義的な価値観や民主主義体制が根付くのは容易なことではないと改めて理解できる。日本もまた幾多の苦難を経て、民主主義国家としての揺るぎない地位を築いた。
歴史の積み重ねを抜きに、一足飛びに理想郷をつくることはできない。独立論を追い求めるより、むしろ50年前の日本復帰こそ、輝かしい沖縄再生の原点であったという歴史的意義を再確認したい。