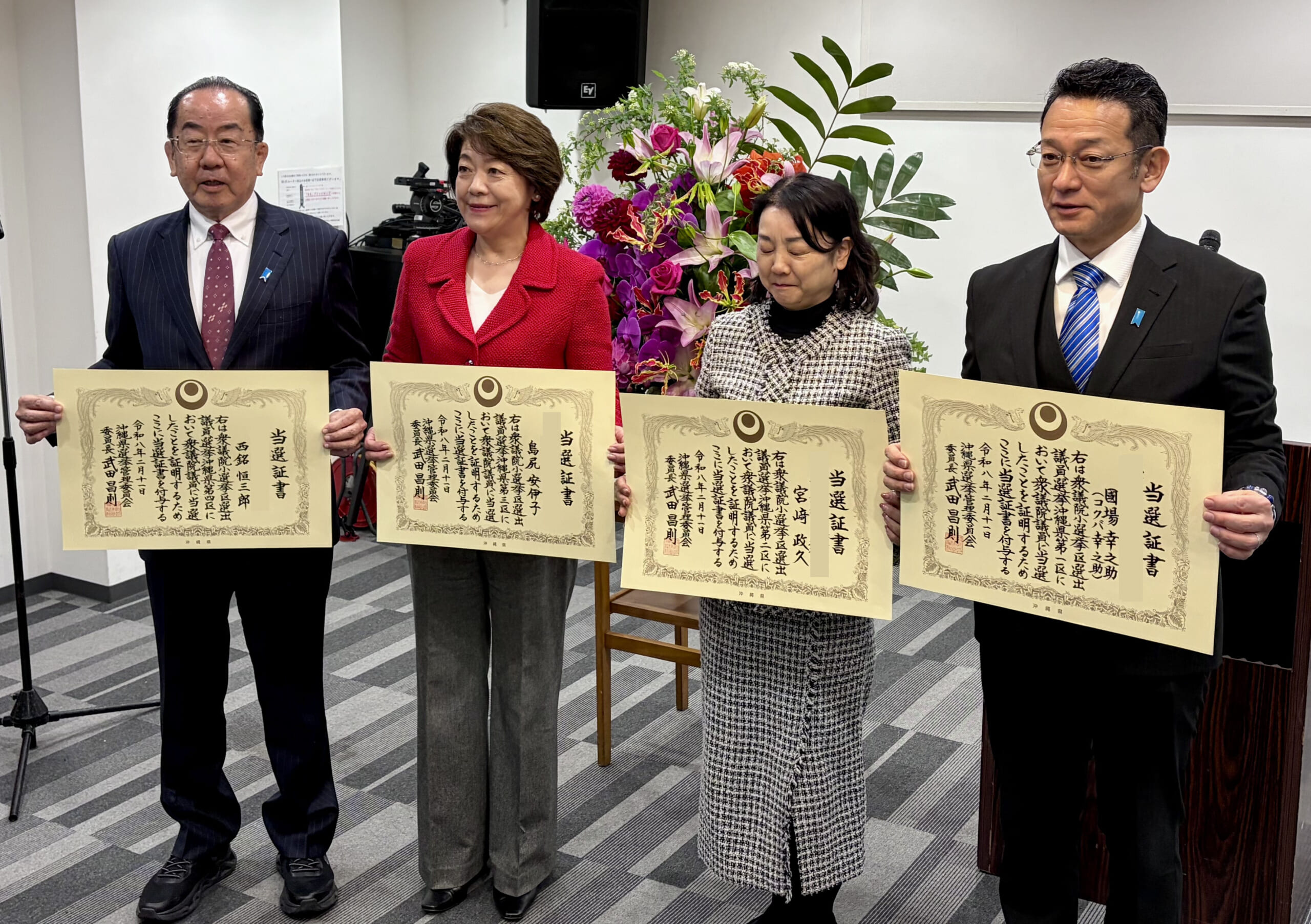【金波銀波】母が旅立った。…

母が旅立った。齢(よわい)五十にして、両親ともに冥界の人となった◆子どものころ「死」は縁遠く、映画や小説の中にしか存在しなかった。それは自分個人に限った話ではなく、戦後世代に共通する特徴でもあった気がする。死が日常の光景だった苛烈な戦時の反動で、戦後、社会は生を謳歌する時代に入った◆作家・三島由紀夫はこう書く。「現代社会では、死はどういう意味を持っているかは、いつも忘れられている。いや、忘れられているのではなく、直面することを避けられている」。現在も葬儀に参列する若者たちは重々しく線香をあげ、合掌はするが、死について深く考える機会にはしない。葬儀などは極力避けたい通過儀礼だから。自分も若いころはそうだった◆だが少子高齢化社会は「多死社会」でもある。いずれ地域によっては2人に1人が高齢者という時代が到来し、戦時中とは違った意味で、死が日常化してくる。良し悪しは別として、死が社会の一部であり、ほかならぬ自分の人生の一部でもあることを、若者の世代も含め、意識せざるを得なくなる◆沖縄の「命どぅ宝」という格言は現在、反戦の合言葉になってしまったが、本来は政治的意味はない。「多死社会」の中で、改めて違う重みを持ち始める言葉だろう。