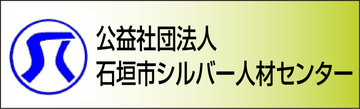知事選では、翁長氏が過去、辺野古移設について「どうせ我々が反対しても政府はつくる。反対したほうが振興策を取れる」という趣旨の発言をしたと暴露された。主義主張が違う保革の政治勢力をまとめ上げるときには、辺野古反対の一点だけで合意できればいいという「腹八分、腹六分」という言葉を使った。「風を読む」政治感覚の鋭敏さで「オール沖縄」全盛期を築いた。
一方で辺野古移設阻止に向けた道筋は開けず、その苛立ちからか、政府批判の発言は過激さを増した。「自国民に自由と人権、民主主義という価値観を保障できない国が、世界の国々とその価値観を共有できるのか」などと日本の民主主義を貶めるような表現を使うことも日常茶飯事になり、本土と沖縄の分断を深めた。
日米が、抑止力のために移設が必要だと決めても「止める」と述べたこともある。移設阻止と日本の安全保障を天秤(てんびん)にかけるような態度にも見え、その政治的スタンスは革新リベラルに接近した。こうした主張は本土で主流を占める保守中道層には受け入れ難く「沖縄の声が本土に届かない」と言われる最大の要因を自ら作った。
沖縄の中でいかに「正義」を自認しても、訴えに普遍性がなければ国や世界は動かせない。現実の厳しさと対峙し、高邁(こうまい)な理想をどこまで実現できるかが政治家の手腕だが、翁長氏は特に晩年、むしろ自らの支持基盤を固めることに腐心していたように見える。
22日には「しのぶ会」も豊見城市で開かれるが、翁長氏を正しく評価するには、その功罪をきちんと振り返ることが大切だ。反基地の象徴として無批判に祭り上げてしまうだけでは、翁長氏の負の側面も引き継がれてしまうことになる。