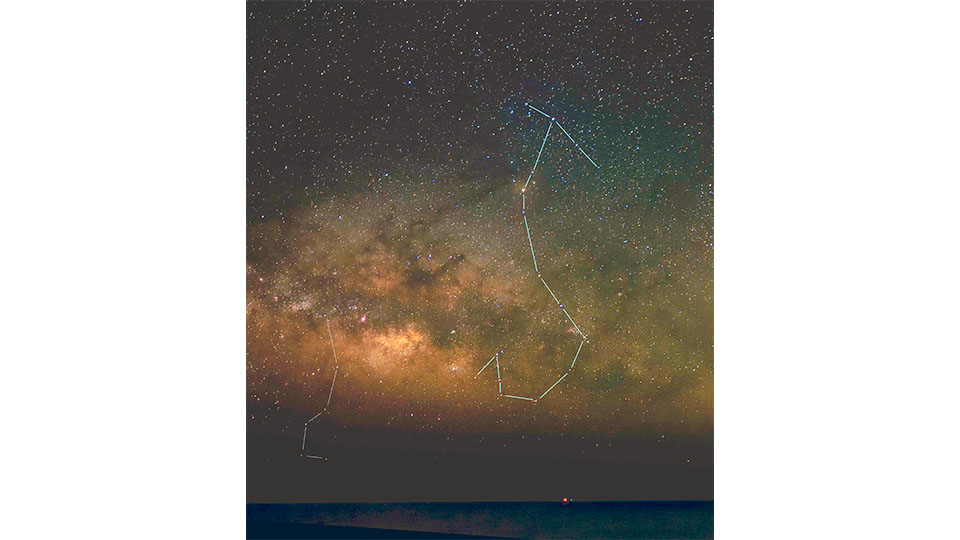【青年弁論大会】母校から見る民族の精神

首里高校は戦後初の沖縄代表として出場し、強豪校相手に奮闘するも初戦敗退。首里高ナインは甲子園の土をバッグに詰め、沖縄へと帰ります。数日の船旅、やっとついた那覇港で彼等を待ち受けていたのは「持っている土を出しなさい」というキャプテンの指示と、海へと捨てられていく甲子園の土でした。それは、外国の土を持ち込んではならないという、米国の法律に触れたためです。ナインの中には、甲子園の土を仏壇に供えようと思っていた方もおられたようですが、その願いも土とともに海へと溶けてゆきました。
この出来事は、当時、祖国復帰を強く願う県民を、さらに熱くさせるものだったようです。
このように私の先輩方は、故郷沖縄を決死の覚悟で守るという精神を体現し、戦後は故郷日本を想う県民を鼓舞させることに至りました。ですから、一中の歩みとは、「故郷を想う」という一つの民族精神を、歴史の一反として未来へとつなぐ役割を担っているのです。
そしてもう一つ、民族の精神を文化的に残している点においても、一人の人物に焦点を当てたいと思います。その方は第一中学校より二つ前の尋常中学校の生徒の一人、沖縄学の父と呼ばれる伊波普猷(ふゆう)です。
伊波は、沖縄の万葉集と呼ばれる『おもろそうし』を言語学的視点から研究し、日本の言語を研究する際は琉球の研究が必要であり、万葉集が「日本人の精神的産物」であれば、おもろそうしは「琉球人の精神的産物」であると述べています。
さらに沖縄にある神話や宗教に対しては、儒教や仏教、道教の分子を取り除くと、日本の神道と同じようなものが残ると言い、「神話や宗教の比較研究は両民族の心理的一致を確かむるに至って必要なもの」とも言っています。
そして伊波は、最期の著書である『沖縄歴史物語』の中で、沖縄戦により甚大な被害を被った故郷へこのような言葉を残しました。「とりわけその文化財のみる影もないまでに破壊し去られたのは、惜しみてもなほ余りあること」。