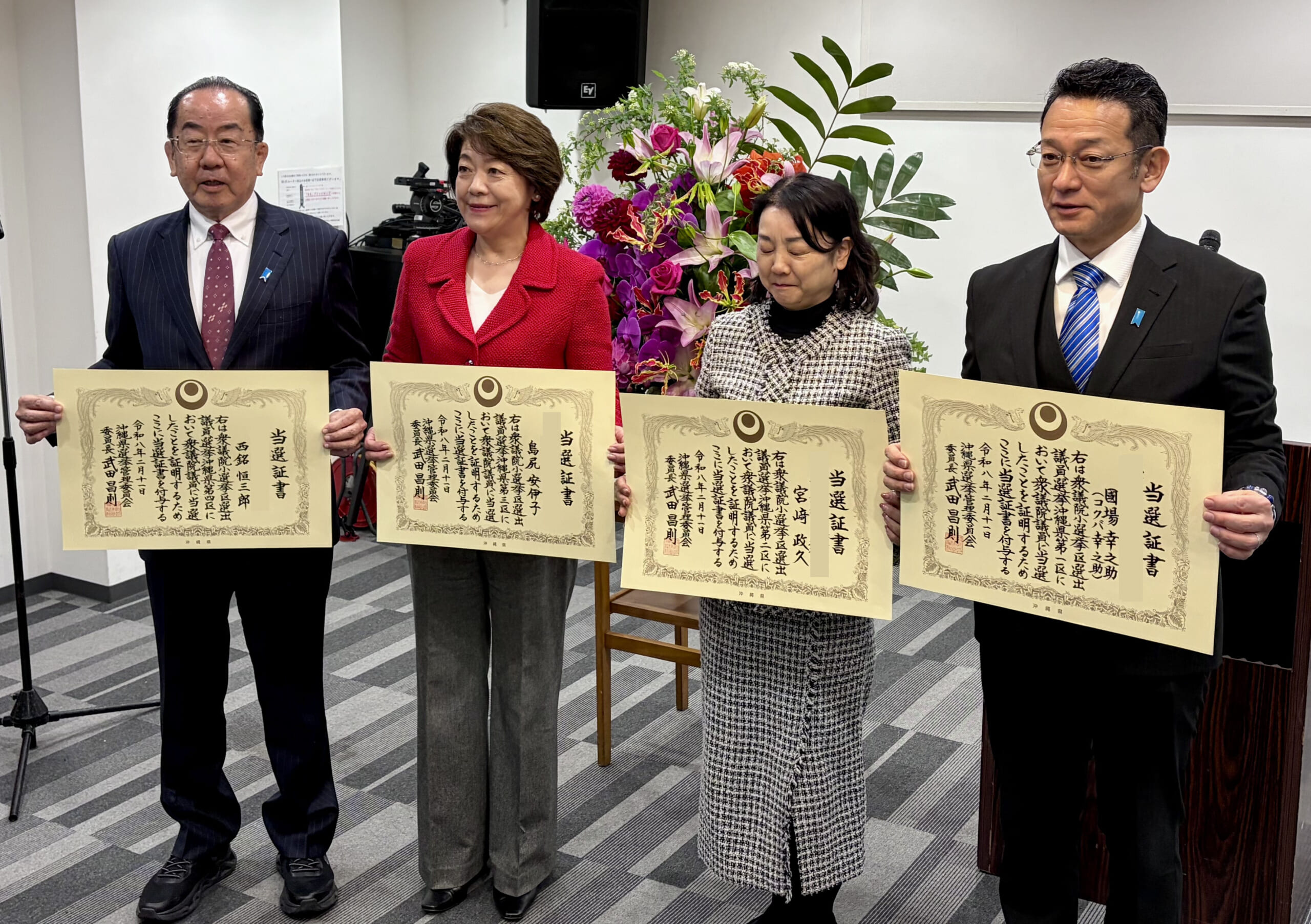【視点】「辺野古阻止」のエネルギー離島に
米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する玉城デニー知事は20日、訪米日程を終え帰国した。「普天間返還と、辺野古新基地建設を見直すよう伝えることができたのは、大変意義があった」と成果を強調するコメントを発表した。だが、米国防総省の担当者は「辺野古移設が唯一の解決策」との姿勢を改めて示したという。辺野古沿岸埋め立て承認を巡る訴訟でも、23日、高裁で県が敗訴した。
しかし、知事は辺野古移設阻止へと精力的に動いている。全国で展開しているキャラバンを11月には北海道札幌市で開き、知事自らが講演する予定だ。
政治的には既に実現不可能に見える辺野古移設阻止のため、血税と行政の膨大なエネルギーが続々と投入されている現状だ。果たしてこのままでいいのか。
そもそも辺野古移設問題は、多岐に渡る米軍基地問題の一つに過ぎない。何のための、誰のための辺野古阻止なのか、それは県政がそこまで力を入れるべき課題なのか、再検証すべきだ。
1996年の日米特別行動委員会(SACО)合意では普天間以外の米軍基地の移転や返還も盛り込まれ、合意に基づいて3年前には米軍北部訓練場の過半が返還された。県は日米地位協定の改定も要望している。
本来なら政府と県が連携し、SACО合意の着実な履行や地位協定の見直しで基地負担軽減を一歩でも先へ進めるべきだが、辺野古が足かせになって両者の対話は停滞している。
だが翁長雄志前知事も玉城知事も、反対しているのは辺野古移設のみであり、SACО合意は基本的に推進の立場だ。しかも日米安保条約の容認も明言しており、厳密には米軍基地に反対ですらない。つまり政府と県の立場は原則として一致しているはずであり、本来、いがみ合う理由は見当たらない。辺野古阻止だけに精力を費やし、政府との不毛な対立を続ける県の姿勢は「木を見て森を見ず」だと思わずにはいられない。
しかも県政の辺野古偏重のせいで、全国では、沖縄の米軍基地問題と言えば事実上「辺野古」だけを指すという本末転倒の状況だ。普天間飛行場の負担軽減をはじめ、米軍基地を巡る多くの課題が忘れ去られる悪影響を生んでいる。